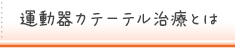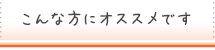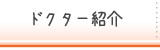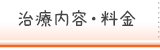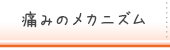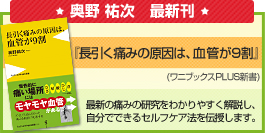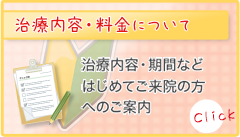人生の時間は有限です。
1日は24時間で、しかも全部使えるわけではありません。
ダラダラしたり、寝ている時間もたくさんありますから
実際に「何かに真剣に取り組める時間」は 非常に限られています。
私は、「何とかして時間を作ろう」という発想はあまり持ち合わせていません。
時間が限られていることに関して、完全に「降伏」しています。
「時間」を相手にするとき、戦う前からあきらめています。
なので、だらだらすることが多いですし、そういう自分も受け入れています。
でも何か大きな結果を出したいと思います。
そのときに強烈に心がけているのは
「最重要のことから手をつける」ということです。
最も難しい、チャレンジングなことから率先して手を出しているとき、すごく成果があがります。
以前、研究生活を送っていました。
そのときの話を例に出したいと思います。
私は、周りから見ると思いっきり「不良」研究者でした。
だれよりも遅くラボに来て、そのくせ5時とか6時とかにあがることもざらにありました。
先輩からは最初から不真面目な研究者だと思われていたと思います。
それでも、自分の研究が2年でBloodという雑誌に載りましたし、3年ちょっとでNature Medicineという雑誌にのりました。どれも一流雑誌です。
もちろんこれらの雑誌への掲載が可能になったのは、私のボスの存在が大きいです。
でもこの2つの論文の実験はほとんど私が手がけています。
この期間に私が最初にとっていた行動指針は
「この結果がでたら、それだけで、とてつもなくすごい!」という、一発ホームラン級の実験から手をつけることでした。
ホームランを打つのは難しく、失敗することも多いのですが。
一度ホームラン級の実験結果が出てしまえば、あとは細かい「安打・凡打」的な実験がいくつか残るだけになります。
「安打・凡打」的な実験は難しくなく、時間をかければできます。
すると、一流雑誌に掲載できるレベルの仕事が完成します。
そうすることで、大きな成果を出すことができました。
「成果を出す」ことに照準を合わせると、必然的にこういう流れになると思います。
※成果主義というのが良いか悪いかは議論があると思いますが、ここでは置いておきます。
さて、私のラボには他にも研究者がいました。
日付が変わるまで研究する人がたくさんいました。
ある日、後輩に研究の進捗を聞いてみました。
「いま自分はこれこれ、こういう実験をしてきた。こういう結果がでている。他にこういうこともやっている」
と答えてくれました。
当然、私より多くの(3倍以上)の実験をしていましたし、プロジェクトの数もたくさん持っていました。
しかし、コアになる実験結果が見当たりませんでした。
どれも「凡打」であり、一流雑誌には出せない状態です。
そういう人たちの研究を見ていると特徴があります。
リスクの少ない実験をしているのです。
「これが言えれば、非常にインパクトがある!」あるいは逆を言うと「この結果が思わしくなければ今までの実験が全て無駄になる」という部分、クリティカルな実験がほとんどの場合で後回しにされていて、残っているのです。
そして周辺の「凡打」的な、どうでもいい実験ばかり手がつけられています。
そして「ここまできたので、いよいよこの実験(大掛かりでホームラン級)をしようと思っている」という風です。
でも最初からそこに突っ込めばいいのです。そこで結果がでれば、迷うことなく残された実験を効率的にできるのです。
私は断言しますが、人間は「何が決定的で、何が決定的でないか」を、無意識で気づいています。
そして、ほとんどの場合は「決定的でない」こと、「大勢に影響のないこと」「できそうなこと」から手を出しています。
こういう研究者はたくさん研究をしますので、「頑張っている」という評価を得ます。
言葉は悪いですが、「頑張っている」という評価が欲しいのです。
私のような人間は決して「頑張っている」とは言われません。
私などは他人から「頑張っていますね」などと言われたら、無茶苦茶腹が立ちますし、はっきり言って反省しますし、やっていることを考え直します。
私は「頑張っているね」の代わりに「おもしろいことをしているね」とよく言われます。
「誰も手をつけていない、そして難しい、そして決定的なこと」に手をつけているからです。
これは特に研究のような分野では大きく差が出る部分だと思います。
でも営業や経営などでも、同じではないかと思います。
なにかの分野に新しく参入したら、まずその分野の最大手の企業と契約が取れたらどうでしょうか?
あるいは宣伝効果の最も高い媒体にいきなり出てしまったらどうでしょうか?
普通の人は、「まだ早い」と言います。
そして数年経っても「まだ早い」と言っていることがほとんどです。
大きなことにチャレンジしようとする人は意外と少ないので、「思っていたより簡単にできてしまった」なんていうことがざらにあるのです。
しかもその過程で普通では見れない景色を見て、普通ではできない経験をすることができます。
「頑張っているか?」「時間を有効に使っているか?」などに気を使わずに
「決定的なことに手を出しているか?」に気を払うことをぜひやってみてください。